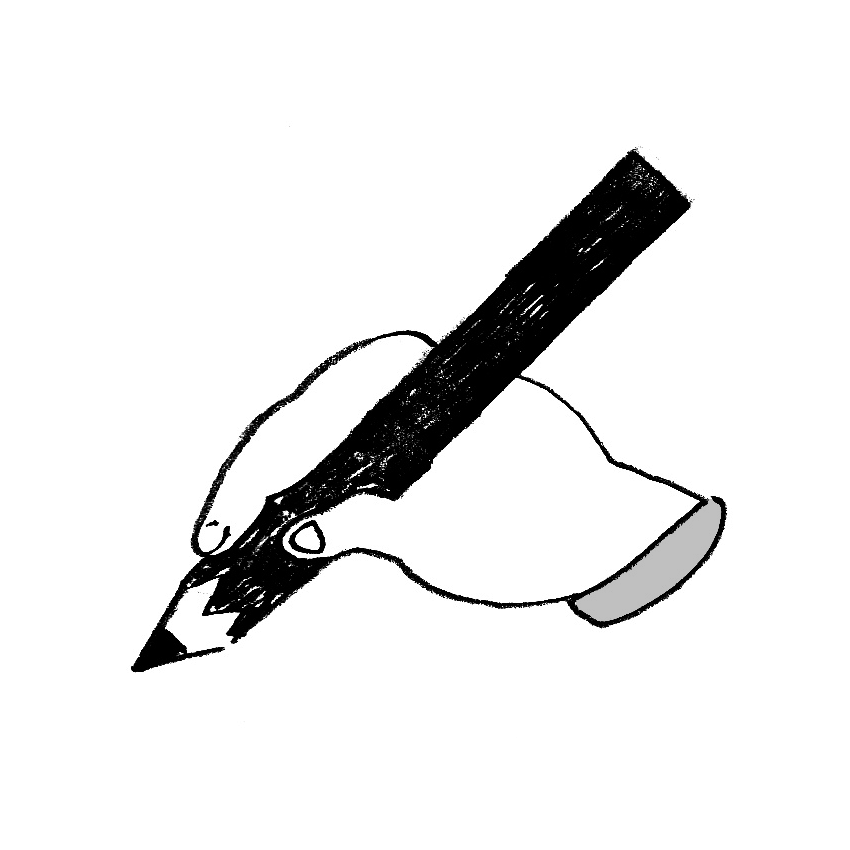小学校六年生のとき。
岩井俊二監督の『打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?』をテレビで見た。それはタモリさんのテレビ番組で、その日は、父親の帰りが遅くて、珍しく遅くまで起きていたような記憶がある。なにげなく居間のテレビは点いていて、父親が帰宅したあとも、最後まで見せてもらって、とにかく僕は感動していた。なんでか分からなかったというのが素直な感想だったけど、でも夢中になってそれを見て、花火大会に行った事がない自分は花火を見たことがなかったし、花火を主人公たちが見れたことに感動していたのだし、引っ越していくこと、両親との距離、離れるだろう友達との距離、転校生だった自分はそういうもんにドキドキして眠れなかった覚えがある。
その日は、父親がもらってきた土産の寿司をたべて穴子が美味しかった。いろいろと覚えている、不思議な日だった、というような感触がある。とにかく感動したそれについて学校で話すことはなかった。大事なことは秘密にしておく、というか、人に話したくなんてないのだった。両親にだって、大事なことは話さなかった。よくわからないけど、そういう風にしていたのだと思う。
今年の夏は、生まれてはじめて花火を撮影したのでした。目の前に現れる、なくなる、その繰り返される刹那を長い時間見つめていたら、星を見つめるのと同じように、人がいて、いなくなる、というような当たり前のことを考えてしまって、でも、その当たり前に何故かとても感動しているのだから、やはり変わらないもんってあるのだなと、何気なくそういうことを発見して、だからこそこの気持ちの分からなさというもんに対して、いまも動かされ続けている自分のことを思って、ふと、その当たり前こそ自分が対峙していくもんなんじゃないかと、そんな凄く単純な気持ちになったのは、何でもない発見だったと思っているのです。当たり前のことを、シンプルにやればやるほど、わからなくなっていくし、何でもなくなっていくけど、それを恐れる必要は感じないし、やはり個人のその風景を美しいと感じたい。それは例えば、先日の飴屋さんの舞台『じめん』においての、石を投げる少年の姿だし、でんぐり返しを繰り返す飴屋さんの身体だし、風に揺れる木々の葉だし、その光景のひとつひとつを確かめるように、装飾せずに、自分も見せたいと思っているし、それを見たいとおもう。それを、そのままで。きっと目の前には大事なひとがいたし、あったし、それがいつか消えてしまっても、そこには絶対にいたし、あったという、そのことを美しいと、絶対に思っているし、言いたいし、見せたい。だから、嘘をつくためには嘘をつかないように、そういう欲望を、その映画から受け取った。
いまだにうまく何かをいうことなんて出来ていない。
僕は被災地をカメラで撮らない。ただ撮らない人間だというだけだ。
友人や、愛する人、その間にあるもんを見つめたい。
大切なひとのことを考えるのは難しく、それはそのまま作品になるとおもう。