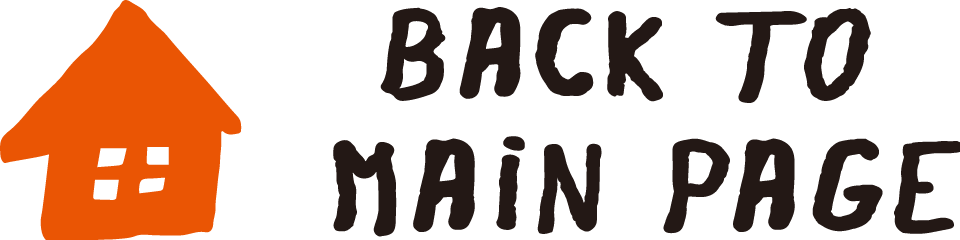今野裕一郎インタビュー 劇場で考察する「衣食住」
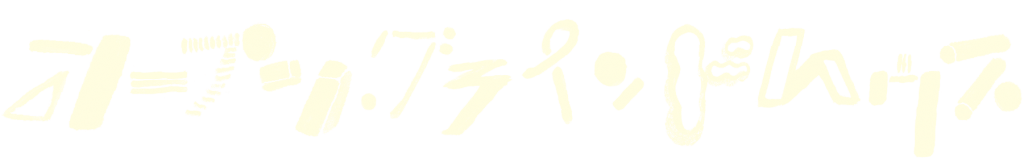
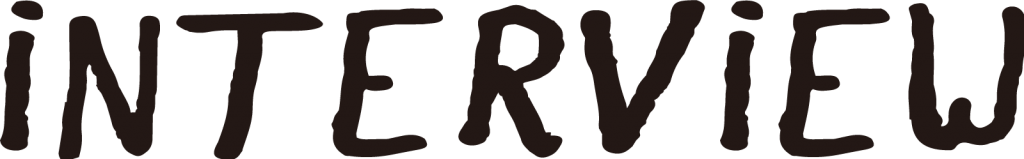
今野裕一郎インタビュー
劇場で考察する「衣食住」
12月にバストリオが展開する『オープン・グラインドハウス』は、吉祥寺シアター主催の「滞在制作」。いわゆる舞台公演のみならず「こどもえんげき部」や音楽家とのコラボレーションツアーなどを展開する彼らが、いかなるインスタレーションを繰り広げるのか。初日目前の夕刻、主宰・今野裕一郎に話を聞いた。

インタビュー・文/田中大介 撮影/和久井幸一
生活の延長線上にあるものを
今回、吉祥寺シアターで滞在型の制作を行なうことになった経緯を教えてください。
吉祥寺シアターさんからのお声がけがあったんです。「12月に何かやりませんか?」という話で、せっかくだからオープンに使ってみたいと思いました。当初は、僕が吉祥寺に毎日通って何かの制作をする「通勤制作」という案があったのですが、通勤というイメージがなんかしっくりこないなと思ったのと、「移動」という行為がフューチャーされるよりは、吉祥寺シアターで6日間ずっとバストリオがオープンする「滞在制作」がいいと思って決めました。
劇場をこれだけ好きに使える機会はなかなかないですし、滞在制作を起点にアイデアが膨らんでいきました。吉祥寺シアターさんからの提案もヒントになっているんです。近隣の人たちに向けた炊き出しをしようという話があったのですが、僕が毎週月曜日に北千住で続けている「こども食堂」という試みを、そのまま吉祥寺シアターに持っていこうということになりました。今回は「こどもおとな食堂」と名付けました。
北千住のBUoY(ブイ)でこどもたちに無料で食事を提供するイベントですね。それを武蔵野市で期間限定的に開催するという……。
そうです。BUoYで食事をつくっている人たちにも協力していただいています。北千住では、こどもは無料でおとなは300円なんですけど、今回はおとなも無料です。
『オープン・グラインドハウス』では、生活の延長線上にあるものを引っ張っていくことができればいいなと思っています。お客さんを招き入れる前に、僕たちがここ(劇場)にいるということから、スタートしたい。劇場なんだけど、生活と紐づくものがあるという意味で、滞在制作します。劇場を劇場ととらえないあり方を探るというか……。
その発想には、2018年5月に急な坂スタジオで公開制作した『扉の開け方』との共通項はありますよね。
急な坂スタジオの経験は確実に影響しています。開放して、最後に発表する基本的な構図は今回と近いです。『オープン・グラインドハウス』が前の試みと違うのは、劇場が通りに面していることですね。これで人の出入りが変わってくるはずです。搬入口をお客さんの入り口にして、吉祥寺シアターのエントランスからは入れないようにします。裏側を表にして流れを回転させたい。それでタイトルに「グラインド」を加えました。
具体的にどんなことをやるのか、詳細を教えてください。
チラシに書いてあることから、さらに刷新されていくと思いますが、大まかに言うと劇場が「広場であり、リビングである」というイメージからスタートしています。人が集まるロケーションということから、お客さんの多寡にかかわらずそこが広場になるという前提がありつつ、食堂をやってコーヒーを出すという、いわば住居のリビングであるという考えがどう共存するかを試したいんです。今回のキーワードは「衣食住」で、やっぱりそれは僕たちの生活と地続きであるということですね。だから、吉祥寺の街で集めた古着や、バストリオのメンバーの黒木(麻衣)が描いた絵をプリントした布などを使って、14日と15日のパフォーマンスで着る舞台衣装にします。
こどもおとな食堂にしても、ただ食事を提供する飲食店ではなくて、店をこしらえていく過程も表現であり、美術化させていくパフォーマンスだと思うんですね。だから、既存のテーブルじゃなくて、イチからつくるんです。店を開くまでの過程も演出の一部です。
なるほど。今野さんやバストリオのメンバー、さらには『オープン・グラインドハウス』に参加する役者さんなどが滞在することで「住」が存在し、食事の提供や衣装制作と、まさに表現と生活が混在するというか。
それを吉祥寺シアターでやるというのが楽しみなんです。
北千住でやっていたこども食堂を吉祥寺に持ってくることで生じる変化は大きいと思います。街も異なりますし、やってくる人たちも違いますよね。
浸透していないから「人が来ない」ということも含めて実験ですね。僕らが舞台でやってきたスタイルで宣伝活動して、その情報をもとに来た人たちとなると、ターゲットが限定されますよね。北千住でも、最初は警戒されてあまり来ませんでした。いきなり無料で食事提供するわけですからね。こどもたちのいる学校や施設に情報を出すことによって、だんだん集まってきましたね。最初に見つけてくれた人は、今でも来てくれますから。もともと貧困家庭や一人暮らしの老人たちに来てもらいたいと考えた有志で始めたんです。その演出部分を僕が担っているという……。
北千住と吉祥寺というまったく空気感の異なる場所でどうなるか、どんな人が反応するのかを楽しみにしています。
贈与と対価と関係性

ちなみに、コーヒーを出すプランは、お金をもらって提供するのではなく、お客さんの「もの」との交換だということですが……。
お金をとると、普通の喫茶店になってしまうので。お客さんが来たらお茶を出しますよね。「お茶を出す」ことでコミュニケーションが生まれる。つまり、何かと何かをつなぐ方法としてコーヒーを出そうと。街の人とコミュニケーションをとる道具として考えたんです。入場無料ですし、利益を求めるつもりはないので、お金ではないだろうと……。
できるだけ武蔵野市の人たちと会いたいんです。入り口にコーヒーのスタンドをつくるので、ここで話すきっかけが生まれて、さらにそこにお金でなく、別のものを介在させてコーヒーで関係性を生み出すというイメージですね。見えるものでも見えないものでもいいから、ものとコーヒーの交換をする。「昨日あったエピソードを話してもらってコーヒーを飲んでもらう」でも「財布に残ったレシートと交換」でもかまわないし、むしろそういうことを期待していますね。
もちろんそれは今野さんのアイデアであり、演出なんですけど、たとえばお客さんからなんらかのエピソードを聞いたとすれば、コーヒーの対価としてお客さんの「ストーリー」を獲得するということでもありますよね。
もちろん、そう思います。それは舞台の演出でも痛感することがあります。役者のなかにあるものを、僕がもらっている気がしますし、事実そうです。ドキュメンタリー映画をやっていた経験からか、被写体にカメラを向けることは暴力的で、役者を舞台に立たせることもそれに近いことだと思っています。だから、できるだけ役者とは与え合う関係でいたいとは思っています。つまり「贈与」ですよね。それが互いにあるかどうか。
お互い贈与することができるか、コーヒーを介してそんなことを考えています。コーヒー屋さんは役者がやるので、豆の選択から何から、彼らがやります。つまり、その役者とお客さんのあいだでコミュニケーションが生まれて、対価として得たものが劇場内で展示されます。それがエキシビジョンになるわけです。
劇場が「演出的空間」となる瞬間

スマートフォンで街を撮るというのも、急な坂スタジオや、2018年7月に三鷹で上演した『ストーン』での方法が引き継がれています。
劇場外の、街の様子をハンティングするという意味で、ドキュメントとして面白いです。僕らが6日間を吉祥寺に滞在した記録として、それこそ暴力的なまでに街が映ってしまうという事実があるけれども、客席にスクリーンを吊ってそれを流します。僕らにとっては初めて見るものでも、吉祥寺の人たちがすでに知っている景色を劇場で共有することはとても面白い行為だと思いますね。単純に、吉祥寺の記録であり、アーカイブとしても面白いですよね。
14日と15日のパフォーマンスはどういうものを考えていますか。
何をやるのかは現時点で決めていないですね。この家に独立した存在というか、いろんなものが生まれると思うんですよ。それを予測しないようにしているので、わからないです。期間中ここで起こったことをダイジェスト的にパフォーマンスするということは考えていません。役者やミュージシャン、役者でない人も参加者にいますが、ここだけで集まっているメンバーではないので……。だから、参加者が途中で「ここにいられないや」と思ったら来なくてもいいんです。
『オープン・グラインドハウス』で起こることは僕も全体を把握できないし、しなくていいんです。コーヒー屋にしても、そこで出会う人に触れて、それを役者が自分で演出していますから。大きな構造として僕が演出の役目ですけど、参加者も演出するし、お客さんの存在も演出の一部になる。大きな意味での「衣食住」が吉祥寺に集まればいいと思っているんです。
2018年12月7日収録